利他学会議レポート:エクスカーション「分身ロボットとダンス」
登壇:OriHime(さえさん)/砂連尾理(ダンサー、振り付け家)/伊藤亜紗(未来の人類研究センター長)
コメント:中島岳志・若松英輔・磯﨑憲一郎
分科会2が終わって雨足は弱まるどころか強くなり、東京都内に張り巡らされているJRや私鉄が次々に止まるなか、今回は目撃だけでなく配信という業務を担っていた焚き火役の私は、自宅から通常1時間のところを3時間近くかけて現地に到着。このエクスカーションを楽しみにするあまり、先生方からの「無理をしないでください」との連絡に耳を貸さずに小刻みながらも確実に進み続け、ついにゴール地のホームに降り立ったときには、富士山に登頂したかのような達成感でコンクリートの大地を踏みしめました。駅の改札を出て眼前に広がった空に出ていた虹を見ながら、以前伊藤先生に教えてもらったおいしいパンやさんに寄ると「さっきは雹が降って地面が真っ白になったんですよ」と店員さん。お互いに嵐を超えて出会えた喜びを分かち合ったのち、大いなる清々しさとともにエクスカーションが行われるセンター拠点へと向かいました。
さて、このエクスカーションは、配信業務を承った役得で、オンライン開催である利他学会議のなか、唯一現場で参加できる時間です。OriHimeのさえさんにお会いできることも大変楽しみにしながら、伊藤先生の到着を待ちました。
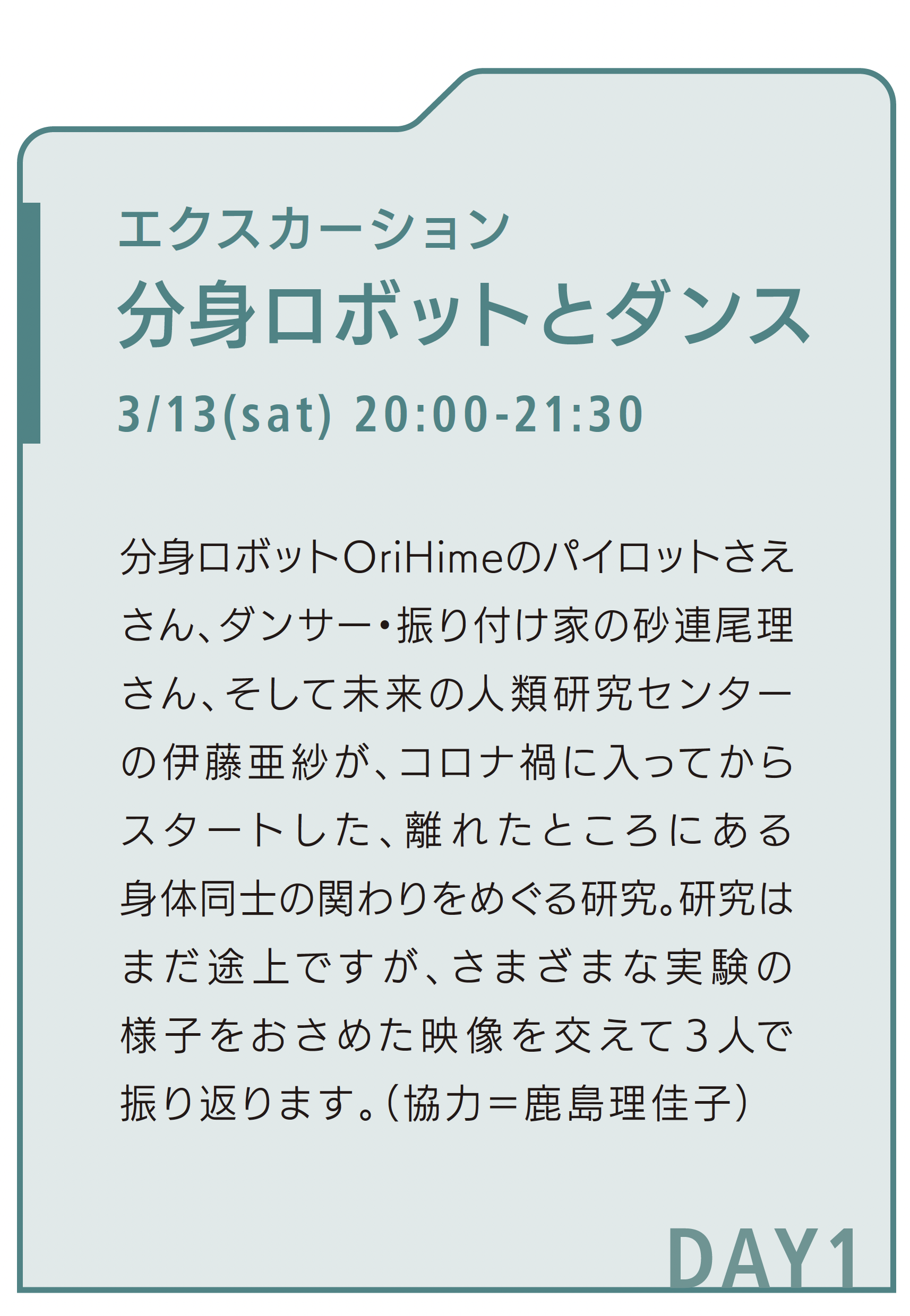
離れているって何なのか 〜オープニングとメンバー紹介〜
20:00になってエクスカーションが始まると、参加者のみなさんが見ている画面には、小上がりに座る伊藤亜紗先生と、その横でちゃぶ台の上に鎮座するOriHimeのさえさんが写ります。そこへ、もう1人のこの研究のメンバーであるダンサー・振り付け家の砂連尾理さん、そしてセンターのメンバー、中島岳志先生、若松英輔先生が次々に登場。磯﨑憲一郎先生は「夜だから」ということで声だけの参加となりました。
●「離れていること」について
物理的に遠い人、会えない人、亡くなっている人など、離れている人とどう関係をもつのか。そんなことを考えたいという伊藤先生とその研究チームのみなさんによるこのエクスカーションのテーマは「分身ロボットとダンス」。これから1時間半強をかけて一緒に考えていただく「分身ロボットとダンス」について、まずは研究プロジェクトの構成メンバーの紹介を聞いてみましょう。
●分身ロボットOriHimeパイロット、さえさん
伊藤先生はとなりでカメラに向かって話しながら、このエクスカーションの間に何十回とOriHimeの顔を覗き込むようにします。そしてOriHimeも伊藤先生を何度も見上げる。お二人のこの仕草だけで何度胸がいっぱいになったことでしょうか。「OriHimeにさえさんを感じる」「存在している、という感じがする」と伊藤先生は話します。「そこにあるのは“さえさんの存在感”で、存在するって何なのか、という定義を更新するようなことが起こっている気がします。」
OriHimeは首の角度を変えたり左右を見回したり、両手を動かしたりすることが可能です。その動きはかなり制限されたものですが、その動き方とタイミング、そこから聞こえるさえさんの声、そして何よりさえさん(がのっているOriHime)を見る伊藤先生の様子から、初対面の私でもこれはきっとさえさんでなかったらまったく違うんだろうな、と思いました。ほかの方がのっているOriHimeには会ったことがありませんが、私があのOriHimeから受けていたのは、さえさんの印象だったんじゃないかと思います(この件については後ほど、この回が終わったあとにおまけでお伝えしたいと思います)。
●ダンサー・振り付け家、砂連尾理さん
高度経済成長期に学生時代を過ごした砂連尾さんは、時代によって「疲弊した身体感を回復したい」という思いで、19歳のときにダンスを始めます。それがダンスだった理由は「当時もっとも敬遠していたものに、何かヒントがあるんじゃないかと思った」から。その後「誰かと踊る」というデュオダンスを16年間続けるなかで、「たまたま障害のある方、その次に老人という、どちらかというとダンスという行動から外れた方と一緒に踊る」ことになった。そしてその後ずっと、踊る・生きる・存在するとは何か、を考え続けることになります。砂連尾さんは、伊藤先生がそのダンスを初めて見た約15年前から「どんどん変身・変化していった」そうです。
最近では、コロナ感染対策として大学や特別養護老人ホームで教えているダンスがオンラインになっているそうなのですが、そこではこんなことが起こっているそうです。「場を共にしているときの“そこにいる”という感じはないんですが、僕がそこに行かないことによって、現場の職員の方が僕の身体を“補完”しようと、僕の代わりに動いてくれるようになった。オンラインになることでコミュニケーションが深まったという側面が一方でありました。」
砂連尾さんからのオンラインを通じた情報を受け取って、砂連尾さんの実体の代わりになろうと踊る職員の方の動きは、「ダンサーで舞台に立てるなあと思うくらい」だったそうです。「ダンスは特権的な身体がやるのではなくて、『媒介となって伝えたい』ことが発生したときにみんなダンサーになるし、それは踊りがもっている本質的な要素なんじゃないかな、と改めて知らされました。」
媒介となって伝えたいことが発生したとき、みんなダンサーになる
砂連尾理
媒体になること 〜動画1「遠隔の触覚」を鑑賞して〜
続いて、爬虫類がとても好きだというさえさんin OriHimeを連れて、吉祥寺の爬虫類カフェ「はちゅカフェ」を訪れている様子。亀やトカゲ、蛇にOriHimeを近づけたり、伊藤先生や砂連尾さんが爬虫類を触った感触を言葉で伝えたりしています。
●触覚の伝え方
お鷹の道付近で砂連尾さんが湧水を飲んだ瞬間、さえさんに「喉のアップを見せて!」と言われたのがいちばんの衝撃だった、と伊藤先生は話します。「水の感覚を伝えるために言葉にしなきゃ、水面をよく見観察させなきゃ、と思っていて、飲むときの喉を見せるというのは思いつきもしませんでした。」
一方、さえさんも、始めは手探りでわからなかったと言います。砂連尾さんのお水の感覚を表すダンスや、手ですくったお水そのものなどから、視覚的に情報を得ようとしていた。ところが、湧水を飲んだときの喉の反応や生理的な動きのほうが情報量が多かった、と言うのです。「砂連尾さんや亜紗先生の喉の動きを見ながら、自分のこれまでのお水の知識を総動員して、自分の喉に落とし込む。そういう触覚の感じ方がそのときはいちばんしっくりきました。」
砂連尾さんはこのさえさんの感覚について「振り付け家から振りをもらうときに同じことをする」と話します。「もらった振りで自分が動いてみて、その振りを身体に“落としていく”。するとそれがあるイメージになったり、体感が増えていきます。」
伊藤先生はこの体験を経て以降、砂連尾さんが水のイメージを表現しようとしているダンスでさえも、「目ではなく喉で鑑賞しているという感じだった」そうです。「さえさんが言うように、能動的に動くよりも、生理的な反射みたいなことのほうが情報量が多いんですね。」この状態を伊藤先生は「自分が媒体になる」と表現します。
動画の後半に出てくる「爬虫類カフェ」でさえさんは、伊藤先生が手を器のようにして大切に蛇を扱う様子を見て「フワフワして心地いい」感覚を味わい、同じ蛇が伊藤先生の体を活発に動き回り出したときの先生の身体の動きを見て「ゾワゾワして気持ち悪い」感覚を味わったそうです。砂連尾さんは、ここで蛇をさわったときの「本当に柔らかくてつぶれそう」な感覚をさえさんにどう伝えようかと考えていたそうですが、「驚きや不快のような、伝えようと思っていないことからくる情報のほうが、かえってさえさんの近くを揺さぶることに気づいた」と話します。
視覚と聴覚に訴えようと意図的にやったことよりも、無意識の動きがさえさんの記憶の力を呼び起こし、その結果もっともリアルな感覚をそこに立ち上がらせたということでしょうか。言葉で意図的に何かを伝えることの難しさと、そうでないところから伝わる奇跡に胸が震えました。
能動的な「アクション」よりも、無意識に「リアクション」として出てしまう動きのほうが、体を超えたものが伝わる
伊藤亜紗
●伝わりやすい媒体、信頼とは
しかしさきほどの映像を見ていると、どうやら砂連尾さんはさえさんの言う通りに動いてくれる、いわゆる“親切な人”ではなさそうです。また、砂連尾さんはさえさんとOriHimeやZoom越しでしか接したことがなく、古くからの付き合いというわけでもありません。そんな砂連尾さんに、さえさんが大きな信頼を寄せる理由について、さえさんは丁寧に話してくれました。
「今まで病気で外に出ることができず、なかなか人と出会う機会もないけれど、OriHimeが存在をそこに運んでくれて、『中にいる私に会いたい』と思ってくれることが信頼につながると思っていました。それはそれであるのですが、砂連尾さんと実験してみて思ったのは、“私の中の身体感覚に耳を澄ましてくれる”ということ。社会的なつながりとは違う、身体的な関わりや遠隔で触覚を伝え合う関係性から生まれる「信頼」みたいなものを、一連の実験をやって感じています。」
一方、普段から「予測していないものを見たときに、その人の身体にどんな揺れが起こるのか、ということに関心がある」という砂連尾さん。OriHimeを通じたさえさんとの関係においても「丁寧に関わることを越境して、何か揺らせないかな」ということを意識しているそうです。そうやって「揺らされて」いるさえさんは、「私が求めるものだけでなく、あらゆる方向から刺激がくるようになった」という新しいやりとりについて、「心地のいいものだけじゃなく、吐き気につながるものやもぞもぞするようなものまで、自分が求めるものだけじゃない感じ方をさせてもらって、毎回新鮮で楽しい」と言うのです。
そんなお二人を見ていて伊藤先生は、「お互いに“こうするとどんな反応をするんだろう”と探り合っている」と話します。「生理的・反射的な動きが重要だという背後には、信頼を作り出すようなある種の駆け引き、探り合いがあって、そこが重要だったんじゃないかなと思います。」
●分身と生身の身体
きっとある世代だと多くの方がそうなんじゃないかと思うのですが、私はこう話すお二人を見ながら、ドラえもんの「かげとりもち」の回を思い出していました。のび太の影と本体が入れ替わりそうになるお話です。OriHimeという分身と、さえさんという生身、さらにこの会の間に何度も伊藤先生が話していた、砂連尾さんという「分身」的存在に思いを馳せると、どこからどこまでが自分かというのはますます曖昧になっていきますが、そんななか、次はさらにその境界を破壊する「体を借りる」という動画が始まりました。
分身になること、分身をもつこと 〜動画2「体を借りる」を鑑賞して〜
後半は砂連尾さんがメイクをするシーン。こちらもOriHimeでさえさんがメイクの指示を出しています。さらにその後半ではメイクした砂連尾さんを伊藤先生がテープでぐるぐる巻きにしますが、このときの巻き具合もさえさんが指示。ぐるぐるに巻かれた砂蓮尾さんは、「電波が悪くて、なかなか声も聞こえにくいときのOriHimeの状態」を体感する、という仕組みです。
●分身と現場の間
現場で「あれ?うまくいかないぞ」とさえさんが思い始めると、「ああ〜♪」と歌とも叫びともつかぬ声を発して若干踊り始める砂連尾さん。それにのっかって、最初はできるだけ的確に「右3センチ」「1センチ奥」というたこ焼きへの指示が、次第に「あああー!」「わー!」という単なる声になっていきます。「OriHimeを抱えている僕は、さえさんの言葉を補完する、言葉で伝え切れていないところを体で表現するような役割だった」と話す砂連尾さんですが、実際には「さえさんと難波さんの間で揺らされる“僕”みたいな感じがあった」そうです。
そのときの体験を、さえさんは次のように話します。「視覚的な部分が欠けた難波さん、OriHimeを通じて空間感覚がズレている自分、そこに砂連尾さんが加わると、その場の空間感覚を共有してスポーツをやっているみたいな気持ちになって、すごく楽しかったんです。」伊藤先生はこの状況について、「制限があるからこそ起こったこと」と言います。
●制限があるということ
また、コロナ対策によってダンスの授業をZoom越しに遠隔で行うことになったという砂連尾さんは、最初「ダンスは絶対にその場にいないとやりづらいと思っていた」。それが、「画面を通して手の動きを大きく間近で見ることができる」「先生がそばにいないからこそ踊れる」「画面OFFにしたら踊るのに恥ずかしくない」と、遠隔授業ならではの利点が次々に発露していったそうです。「制限があることで、意外と踊れる体、接近できる体が獲得できることがわかった。」
動画2の後半に出てきた、さえさんが砂連尾さんに遠隔でメイクを施すシーンでも、同じことが起こっていました。「生身の身体だったらあんなに砂連尾さんに近づけない」とさえさん。制限があるからこそできた遠隔でのメイクによって、砂連尾さんやさえさんはどんな感触を得たのでしょうか。
制限があるからこそ、近づいたり感じたりできる部分がある
さえさん
●遠隔で気持ちを移植する
一方、砂連尾さんを「振り付け」た側のさえさんは、「メイクが終わったときの砂連尾さんの“ぽわん”とした笑顔は、自分が普段メイク完了したときに鏡の前でつくる顔と同じだった」と話します。アイラインをひいた目元や、口紅をつけた口元という具体的な部分ではなく、メイクをした自分の顔を鏡で見たときに発生する「自分の姿に媒介された自分の気持ちみたいなもの」が砂連尾さんに移植されたのではないか、と伊藤先生。「触覚や視覚の情報ではなく、その人の内側を、それが外に出てきた状態と一緒に遠隔で運ぶことができる、ということがメイクを通して見えてきました。」
存在にふれる 〜動画3「ここにいない人と踊る」を鑑賞して〜
同じ年に砂連尾さんのお父上ががんになり、二年半の闘病ののち、2019年に亡くなります。あとを追うようにお母様も亡くなられ、2020年春以降のコロナ禍で砂連尾さんは、「喪失感とともに両親のことを考える時間が多かった」。ここでさきほど動画1でタコ焼きをつくっていた難波さんの登場です。コロナ禍になったばかりの頃、伊藤先生がある不安を難波さんに相談したところ、難波さんはZoom飲みを提案。1年以上経った今も定期開催が続いているという、月に一度、3時間ほどの「コロナビールの会」が始まりました。ここに誘われた砂連尾さんは、のちに加わるさえさんとここで出会い、伊藤先生との研究チームが発足します。
研究チームに参加することになって、「亡くなった両親や一緒に踊った人のことを考えることと、さえさんと関わることがつながった」と話す砂連尾さんは、今回の研究と並行して、Zoomを通して誰かと踊ったり、両親の写真の前で踊ったりするという映像作品をつくりました。この日、3つ目の動画はこの砂連尾さん作の「ここにいない人と踊るためのエチュード」です。
●触覚と記憶、存在
ある植物状態の患者さんの看護をしていた看護師さんは、その患者さんが亡くなってからものすごくその人の体の感触を思い出す。生きているときは一方的に看護をしていると思っていた看護師さんは、「実はその人に自分は体をさわられていたんだ」と気づきます。つまり、看護師さんが手で患者さんをさわるとき、患者さんも身体で看護師さんの手をさわっていた、ということですね。たとえば「体位を支えるときに、その人もがんばろうとしていたということが、感触として、私の手に対する思いのようなものとして、手に残り続けているんじゃないか」と看護師さんは考えます。
「砂連尾さんの“ここにいない人と踊る”というのは、触覚の記憶を拡張していった形なのかな。いっぱい蘇ってるんだろうな」と伊藤先生は話しました。
触覚的な記憶は残るもので、亡くなってからも関係が続き、変化していく
伊藤亜紗
砂連尾さんがコロナ以前から「ここにいない人と踊る」をテーマとして考えてきたのと同じように、コロナで世の中が非接触へと移行する前から外出が難しく、ずっと家にいて「存在をだれかにふれてほしい」と思って生きてきた、というさえさんですが、OriHimeに出会って以降、そしてこの実験に携わっていくなかで、「ふれられないけど、ふれられる」という遠隔の可能性を強く感じているそうです。「相手の感覚や存在に思いを馳せることが、生身で会っているときよりも、頭の中で増幅されていくのかな、と思います。そういう気持ちが強いほど、信頼関係、存在のつながりの強さに結びついていくのかな。」
そこに実体がなくても、存在にふれてもらうことはできるのかもしれない
さえさん
●入り込む力と自己満足
これまで、舞台上で人に見せる身体を作るため、モダンダンス→バレエ→合気道→ヨガ→太極拳・気功、とあらゆる体の動きを学んできた砂連尾さんは、「植草盛平(合気道の創始者)の身体や言葉がこういうふうに形になっているんだ」「バレエをつくってきたいろんな人の声や身体が集積されて今こうなっているんだ」ということを体で発見していきます。そしてそれは「自分の身体でありながら、もう1つ他者の身体を入れていく、という身体の多重性」を実感することでもあったそうです。「そういうものすごいバランスのなかで、“ふれにいく“ということをやっている気がします。」そしてこの身体の多重性が、「入り込みながらも変に満足しないための身体」だと話します。
「僕の身体には、いろんな人の体や知恵が入り込んでいる」
砂連尾理
「OriHimeと体の違いって、実はそんなにないのかも」
伊藤亜紗

ディスカッション
●存在にふれる
中島先生は岡江久美子さんとは実際に面識はなく、ただ「よく家のテレビで『はなまるマーケット』がついていた」という程度の間柄です。しかし彼女が亡くなってから、中島先生のなかに何か大きな変化が起こりました。「亡くなってから、彼女の存在が自分の日常のなかにあったんだ、と気づかされた。」これは砂連尾さんがさえさんに感じている「会ったことがないがゆえに存在にふれる」という問題につながるのかもしれません。
砂連尾さんはバレエをやっていて、「実際にこの動きをつくってやっていた人から、今これを受け継いでいる」と思ったとき、「こんな感じかな、と思いながらその動きをやってみること」を追体験をするような感覚を持つことがあるそうです。「それは、会ったことのない死者の存在が増えて、死者だらけのなかにいるという感覚です。“木はちゃんと僕を見ているな”という感覚にも似ています。」
そしてここで若松先生の登場です。若松先生はこのエクスカーションについて、「こんな話で今日1日が終わると思ってなかった」と言って、次のように話されました。その言葉が、まるで若松先生の「詩」の一編のようなので、一部そのままお届けいたします。
存在の「存」は時間的にあること、「在」は空間的にあること
永遠にこの世にある、というのが「存在する」ということの本当の意味
「死」は、その存在を隠すことではなく、より存在を明らかにする出来事です
「死」は、遠くに行くことではなく、私たちの傍らに来ること
私たちが死者をさがすとき、いちばん最後に探すのが「傍ら」
このことが私たちをときに苦しめる
私たちは死者が遠くに行ったと思うから、遠くを探す
だけど遠くまで探しても、目に見えることもふれることもない
ある日、自分の傍らに、自分が気づくずっと前からいたんだ、と気づくとき
その人の人生は変わってくる
さらに若松先生は次のように話しました。「みなさんと過ごしたこの1時間半の新しいタスクとして“存在の共有”があります。目の前のことだけじゃなく、その人が今まで生きてきた過去も、この人が生きていくであろう未来も共有できるということが大事で、それは生死を超えて起こります。」
「私たちは接触でつながっているわけではなく、存在でつながっている」
若松英輔
●無機質な形状
この質問を受けて砂連尾さんは、「それなりのインパクトはありながら“溶けやすい”、しっかりした形はあっても途中からその形状を“忘れられる”、それがOriHimeの内部に入っていこうとしやすい感覚につながっている」と話します。一方、現在、分身ロボットカフェDAWNでOriHimeにのって働いておられるさえさんは、OriHimeが無機質で想像の余地を与えてくれる形状だからこそ、フラットな関係性で働ける、と話します。「もしこれが本人の姿を反映したものだと、年齢や性別を想像して無意識に相手のイメージを自分のなかで作り上げてしまう。第一印象で関係性が決まっていたかな、と思います。」
ここで中島先生は、分科会1で三宅美博先生が話された無表情のからくり人形「弓引き童子」の話をします。それが無表情、すなわち「非完結」であるがゆえに、こちらには笑って見えたり悲しんで見えたりする、というお話でしたが、中島先生は「その関係性の“間(ま)”がとても重要なんじゃないか。」と言います。たしかに、すべてを「わかって」いて、想像の余地がない関係があるとすると、それはとてもしんどそうです。
「非完結なものとの関係性にある“間(ま)”がとても重要」
中島岳志
私はリハーサル時に一度これを見ていたのですが、それでもこのときもう一度ショックを受けました。ここで少しだけ未来に飛びますと、この日はほとんど何もコメントしなかった磯﨑先生が、このさえさんが抜ける瞬間を見て以降、利他学会議の間中この話しかしなくなることを考えると、画面を通して見ている方々にもあの衝撃は伝わったのではないかなと思います。
「さえさんが帰ったので、私たちも帰ります」という伊藤先生の言葉で、エクスカーションは終了しました。最初に少しお知らせしたように、私はこの場所にたどり着くのに結構な道のりだったわけですが、その距離と時間がほんの些細なものに感じられるほど、いろいろと遠くへと旅して帰ってきたかのような1時間半強でした。
さて、ここでやっと利他学会議の第一日目は終了です。ここからは上記で私が若干の嘘をついてしまったことを告白するコーナーです。「私があのOriHimeから受けていたのは、さえさんの印象だったんじゃないかと思います」と上のほうでお伝えしましたが、それはリアルタイムで思っていたわけではありませんでした。実はあの現場にいるときは、配信状況と流れのことで頭がいっぱいで、せっかくそこにさえさんin OriHimeと伊藤先生がいるのに、まったく注意を払えていなかったんです。私がさえさんのことを知っているような気がし始めたのは、さえさんの声やお話の内容を思い出しながら帰った電車のなかでのことでした。
さあ、おまけも終わりましたし、今日はみなさんも疲れたでしょうからゆっくり休んでください。私も泥のように寝ます。明日は利他学会議の第二日目、分科会3から始まります。

