沈黙しないストレンジャー:音楽、マイノリティ、多文化共生、日本
ヒュー・デフェランティ、宍倉正也、米野みちよ 編
シンガポール国立大学出版社、2023
私は川越に住んでいる。川越は東京と秩父山地の間に位置し、かつてはほぼ独立した貿易都市であった。現在は「歴史的遺産の風景」を利用した観光業と伝統的な小規模農業という2つの堅固な地域経済を両輪としているためか、明らかに保守的な傾向を持つ郊外の拠点となっている。しかし、西側地域の霞ヶ関の眠ったような通りを歩いていると、しばしばネパール人、ベンガル人(バングラデシュとインドの両方)、ベトナム人、広大な中国全土からやってきた若者たちの会話の音に浸される。それを聞くと、"ああ、モノカルチャーの日本の郊外がやっと変わっていくのだな・・・"と思う。
2019年は日本の「移民元年」と呼ばれた。戦後初めて公に認められた日本の「移民時代」である。皮肉なことに、長い間待ち望まれていた日本の労働力不足の危機に対する政府の協力に基づく対応が、新型コロナウィルスの出現によって同年末から行き詰まってしまった。その後3年間の世界的な非常事態を経て、特定技能ビザによる入国者数が2018年末の法律で許容されていた水準に向かって増え出したのは、ようやく 2023年のことである。その結果、この悪名高い偏狭な社会において、ダイナミックな人口動態の変化の勢いが、いま目を見張るほど加速している。シドニーで育ち、人生のあいだ断続的にそこで生活していた私にとって、現在日常的に出会う南アジアや東アジアの若い人々は身近な存在である。しかし、川越西部の地元の大部分の人々、つまり関東平野の片隅で居心地の良い農耕生活を送っていた世代から1、2世代しか離れていない人々にとっては、これらの外国人たちはまったくのよそ者(赤の他人)なのである。
よそ者(ストレンジャー)とは? テクノロジーに支えられ、2020年代にこの英語の言葉はますます奇妙(strange)なものになった。つまり極めて奇妙に、少なくとも不可解に使われるようになった。50歳以下のほとんどの人が、プライベートな時間の大半を、オンライン上の「見知らぬ人」、特にソーシャルメディア上の実名や顔を知らず、見ることもない人たちの言動を見たり、読んだり、聞いたり、さらには反応したりすることに費やしている。他の技術先進国と同様、これは2023年の日本の社会にも当てはまるが、対面での人との交流のしきたりはまた別である。外国人の「よそ者」(一般に観光客とみなされる短期滞在者を除く)の扱いに関する歴史的な傾向や規範が存続する限り、文字通りの声と比喩的な声が聞き取られ、それらに対して耳を傾けられるようになるまで、こうした文化的・言語的新参者との関係における利他は、おそらく意味あるものとして想像できないだろう。しかし、それが実現するまでは、移民マイノリティのメンバーは自分の存在を音で宣言することを選ぶことができる。つまり、彼らは「沈黙しない」存在でありうるのだ。
沈黙しないよそ者とは?「多文化共生」という15年前から出回っているスローガンの官僚的なレトリックがあるにもかかわらず、移民が日本の公的生活に参加するためには、国や地域の文化規範に徹底的に同化することを条件とするという期待が根強く広がっている。その結果移住者は、日常生活で「日本人」と円滑に交流できるように、適切な振る舞い方と国語の話し方や読み方を十分に学ぶまでは、目立たないように、言い換えれば「沈黙している」べきだということが、ほとんど語られることのない前提となっている。川越西部の街を歩いた私の経験からは、文字通りのレベルではそのようなことは起こっていないことがわかる。霞ヶ関の周辺部においてさえ、裏通りを支配する静けさに近い状態は、しばしば聞き慣れないアジアの言語のざわめきによって破られる。
比喩的に言えば、移民マイノリティはどこでも社会文化的に弱い立場にあるが、彼らを黙らせ彼らの存在を公的な言説から排除しようとしても、「沈黙」することはあり得ないし、そうあるべきでもない。
利他が他者指向であるならば、この国で急速に増加している文化的他者に対する公共的、市民的、個人的な対応は、利他の可能性を帯びていることになる。繰り返しになるが、「多文化共生」は2008年頃から広く親しまれる政策のスローガンとなってきたが、それは当センターのメンバーが「利他」の本質として提唱してきたいくつかの特徴を実際に示しうるような概念である。つまり、(この場合は文化的・民族的)他者が何を発言しコミュニケーションしているか耳を傾けること、彼らのニーズや行為に影響を受けて自分の考えを変える余裕があること、あらかじめ設定した自分の意図や信念を相手に押し付けないことである。
このような状況の中で、パフォーマンス文化、特に新参者である移民のマイノリティの音楽やダンスは、受け入れ側の日本人だけでなく移民自身も含めて、異文化間や主観間の経験の橋へと人々が決定的な第一歩を踏み出すよう誘う、効果的な媒体となり得る(ただし必ずしもそうなる必要はない)。そこでは利他の条件が常に生じうる。「音楽は世界共通語である」という決まり文句は、民族音楽学、音楽知覚認知学、心理学の分野での研究によって何度も否定されてきたことであり、私は決してその決まり文句に同意しない。しかし、文化的他者が音楽やダンスのパフォーマンスを体験し楽しむことで、他者への肯定的な働きかけを促すような態度において明白な変化が生じると主張することができ、それはある程度経験的に実証されている(Clarke, DeNora, and Vuoskoski 2015参照)。
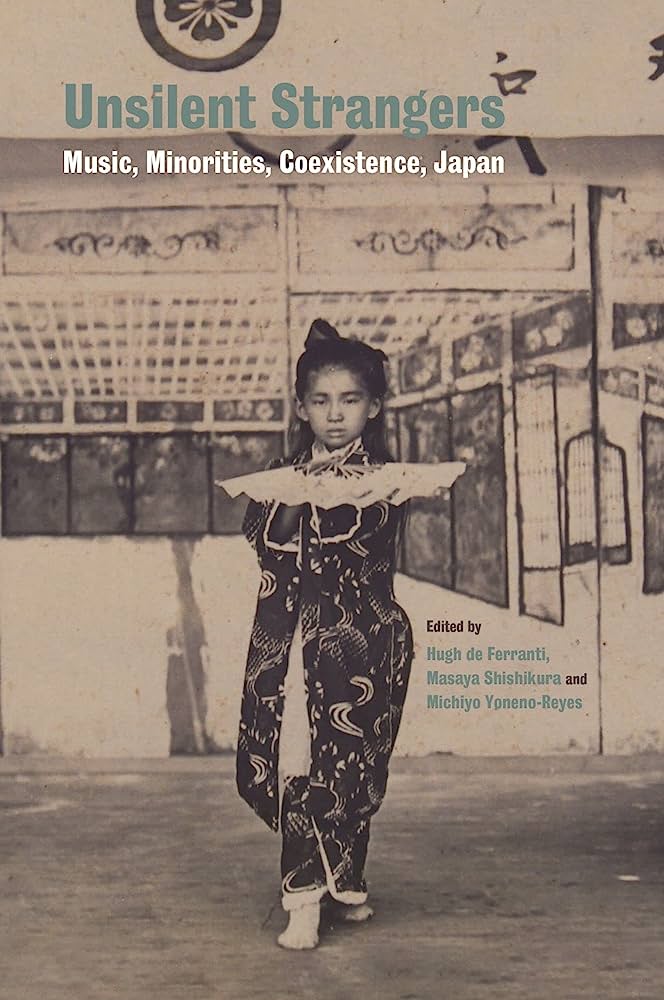
本論文集は、2017年から2020年初頭まで行われた科研/JSPSの共同研究プロジェクト(科学研究費補助金B、17H02285、主任研究者Hugh de Ferranti)の成果の一つで、シンガポール国立大学出版社(National University of Singapore Press)と協力しながら、米野みちよさん、宍倉正也さんとともに2年半にわたって行われた執筆と共同編集の末に生まれた。本書はかなり長期にわたって胚胎されたため、編集作業の最後の12ヶ月は私が「未来の人類研究センター」の会員になった最初の年と重なり、利他の視点から本文を読むことが可能になった。
「未来の人類研究センター」の利他プロジェクトに関連して、東京とその周辺の新たにやってきたマイノリティたちと、戦前移民であった日本人に関する執筆者たちのケーススタディから、利他に合致する発見をいくつか紹介する:
i. マイノリティグループは、音楽とダンスを相互に有益な形で展開するかどうか自分たちで選択を行う。東京のネパール人、南インド人、フィリピン人、日系ブラジル人、イラン人、「国内移住」アイヌのケーススタディでは、音楽家が自分のパフォーマンスを多数派や「ホスト」である他者に向けて位置付ける状況もあれば、音楽活動をコミュニティ内に留め、プライベートなものにし、周囲の日本人や他の民族には全く知られていない状況もある(Small 1998)。
ii. 一般的な予想に反して、移民グループのメンバーと特定の少数民族の音楽・舞踊に詳しい日本人音楽家とのコラボレーションは、必ずしもホストの文化の音楽への相互関心につながるわけではない。これは特に、井上貴子氏が南インドの「滞在型移民コミュニティ」と呼ぶもので、彼女の30年にわたる演奏家および研究者としての関与に基づくケーススタディで浮き彫りにされている。
iii. 移民としての日本人に関する比較歴史研究の中でも戦前のオーストラリアに関する私の研究は、(やはり当初の予想に反して)当時異なる「人種」と呼ばれていた人々が(口頭ではほぼ認識されなかったものの)実際の相互依存を音楽で表現することを通じて、異文化の間で生じる情動を伴った体験を可能にするような実体験と、地域の文脈が存在したことを示している。
参考文献:
http://www.musicminoritiesinterculturalexperience.hdf.ila.titech.ac.jp
Eric Clarke, Tia DeNora, Jonna Vuoskoski. 2015. “Music, empathy and cultural understanding”
Physics of Life Reviews 15 (2015) 61–88
https://doi.org/10.1016/j.plrev.2015.09.001
Small, Christopher. 1998. Musicking: The Meanings of Performing and Listening.
Middletown, CT: Wesleyan University Press.

