研究会レポート Vol.2
ゲスト:久堀徹(科学技術創成研究院長)
2020.06.19
ゲストを迎えて開催される未来の人類研究センターの利他研究会第2回は、2020年4月21日に東京工業大学の久堀徹教授をお招きして、ZOOM上で行われました。
久堀先生は、2018年4月から2020年3月まで、東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所の所長を務められ、この4月に科学技術創成研究院の院長に就任されています。久堀先生はご自身の研究を通じてどんなことを考えていらっしゃるのでしょうか。また、久堀先生の研究とセンターのメインプロジェクトである「利他」との関わりはどんなところにあるのでしょうか。
わかりやすい例えをふんだんに盛り込みながら、久堀先生はまずご自身の研究の中心である、「植物のエネルギー変換システム」について、お話ししてくださいました。
人間が必要とするエネルギー
私たち人間は、日々どのくらいのエネルギーを使って生きているのか、ご存知でしょうか。久堀先生は、東京マラソンに参加されたご経験があるそうですが、これを完走するにあたって使ったエネルギーが2,843kcal。これは成人男性が通常1日に必要とするエネルギー量とほぼ同等だそうです。しかし、今人間が1日に消費するエネルギー量は、食べ物だけではありません。生きるのに使うエネルギーがほぼ食糧摂取だけだった100万年前から、暖房、調理、農作業、輸送、工業、農業、商業と人間の活動の幅が広がっていくにつれ、自然エネルギー、化石燃料、電気エネルギーとその幅が広がると同時に人間社会のエネルギー消費量は増え続け、2018年には一人あたりのエネルギー消費量は410,000kcalにまでなっています。つまり、私たちは人が一人生きるのに必要な量の200倍くらいのエネルギーを消費して暮らしているというわけです。
そして私たちは消費するエネルギーの多くを「太陽光」に頼っています。さらに、植物が太陽光を使って光合成によってつくり出すエネルギーをも、私たちはふんだんに使っています。その一方で、2020年現在、私たちは熱帯雨林の減少、砂漠化、宅地開発といった人間側の事情によって植物を地球上から減らしている。すなわち、私たちは自ら「使える酸素を減らしていっている」ということになります。
そして私たちは消費するエネルギーの多くを「太陽光」に頼っています。さらに、植物が太陽光を使って光合成によってつくり出すエネルギーをも、私たちはふんだんに使っています。その一方で、2020年現在、私たちは熱帯雨林の減少、砂漠化、宅地開発といった人間側の事情によって植物を地球上から減らしている。すなわち、私たちは自ら「使える酸素を減らしていっている」ということになります。
なぜか裏表、動物の呼吸と植物の光合成
人間は植物がつくり出すエネルギーを利用しているというのは、具体的にどういうことでしょうか。私たちは呼吸によって酸素を取り込まないと生きていけませんが、この「呼吸」という営みと、植物が太陽光を浴びて行う「光合成」の仕組みは、科学的には以下のようになっています:
呼吸: 糖を分解してCO2を吐き出し、最終的に酸素を使って水をつくり出しながら、ATP(エネルギー物質)をつくる(→運動や代謝に使う)
光合成: 光が当たると水を分解してATPをつくり、CO2を固定して糖をつくり出す
こうして見てみると、同じルートを逆側からたどっている感じです。これらはいずれも「電子伝達系」と呼ばれるシステムだそうで、「水に対する反応と合わせてプロトンを膜の一方向に輸送する動きによってATPをつくり出す」、という仕組みにおいてはまったく同じ。すなわち「呼吸」と「光合成」の営みは、裏表のような関係になっています。そして、その植物の働きによってつくり出されるエネルギーを人間が利用している。「つまり、我々は植物が隣にいないと生きていけない」と久堀先生は言います。
私たちの側から見ると、植物と私たちの関係がなぜこんなにうまいことできているのか、不思議な気持ちになりますが、実は「呼吸と光合成の進化的な根は一緒」なのだそうです。「いちばん最初に生まれたと言われる光合成生物が、1つはミトコンドリアになり、1つは葉緑体になった。もともと同じ電子を運ぶシステムをもったものが2つに分かれて、やることが反対方向になったんですね。」と久堀先生は話します。
さらに驚くことに、呼吸する私たちと光合成をする植物が、それぞれその機能を最初どのように手に入れたかというと、なんと、それぞれの祖先である生物が、一方はミトコンドリアを、もう一方は葉緑体を「食べた」から。「普通は食べたら分解しちゃうんですけど、それをうまいこと自分の細胞の中に取り込んで、その機能を利用した」ということなのだそうです。
こうやって、ある細菌を「食べる」ことで自分のなかの1つの機能にしてしまう理由はわかっていないそうですが、その後進化を遂げた私たちや植物のなかにその痕跡がしっかり残っているというからさらに驚きです。その痕跡とは、生物を分ける「膜」。生体膜の驚異的な役割については、大隅先生と伊藤先生、中島先生との鼎談でも熱く語られていましたが、食べられた側が食べた側の生物に機能となって残っている場合、食べた側の膜と食べられた側の膜で「二重膜」になっているそうなのです。だから、葉緑体も、ミトコンドリアも、二重膜。何遍も食べられ続けて三重膜、四重膜になっているものもあるそうで、生物の進化の歴史には本当に目を見張るものがありますね。
呼吸: 糖を分解してCO2を吐き出し、最終的に酸素を使って水をつくり出しながら、ATP(エネルギー物質)をつくる(→運動や代謝に使う)
光合成: 光が当たると水を分解してATPをつくり、CO2を固定して糖をつくり出す
こうして見てみると、同じルートを逆側からたどっている感じです。これらはいずれも「電子伝達系」と呼ばれるシステムだそうで、「水に対する反応と合わせてプロトンを膜の一方向に輸送する動きによってATPをつくり出す」、という仕組みにおいてはまったく同じ。すなわち「呼吸」と「光合成」の営みは、裏表のような関係になっています。そして、その植物の働きによってつくり出されるエネルギーを人間が利用している。「つまり、我々は植物が隣にいないと生きていけない」と久堀先生は言います。
私たちの側から見ると、植物と私たちの関係がなぜこんなにうまいことできているのか、不思議な気持ちになりますが、実は「呼吸と光合成の進化的な根は一緒」なのだそうです。「いちばん最初に生まれたと言われる光合成生物が、1つはミトコンドリアになり、1つは葉緑体になった。もともと同じ電子を運ぶシステムをもったものが2つに分かれて、やることが反対方向になったんですね。」と久堀先生は話します。
さらに驚くことに、呼吸する私たちと光合成をする植物が、それぞれその機能を最初どのように手に入れたかというと、なんと、それぞれの祖先である生物が、一方はミトコンドリアを、もう一方は葉緑体を「食べた」から。「普通は食べたら分解しちゃうんですけど、それをうまいこと自分の細胞の中に取り込んで、その機能を利用した」ということなのだそうです。
こうやって、ある細菌を「食べる」ことで自分のなかの1つの機能にしてしまう理由はわかっていないそうですが、その後進化を遂げた私たちや植物のなかにその痕跡がしっかり残っているというからさらに驚きです。その痕跡とは、生物を分ける「膜」。生体膜の驚異的な役割については、大隅先生と伊藤先生、中島先生との鼎談でも熱く語られていましたが、食べられた側が食べた側の生物に機能となって残っている場合、食べた側の膜と食べられた側の膜で「二重膜」になっているそうなのです。だから、葉緑体も、ミトコンドリアも、二重膜。何遍も食べられ続けて三重膜、四重膜になっているものもあるそうで、生物の進化の歴史には本当に目を見張るものがありますね。
植物はスイッチを持っている
植物の重要性を考えながらエネルギーについて研究されている久堀先生の研究室では、「呼吸」と「光合成」の両方で行われている「ATPをつくり出す」仕組みについて研究を進めています。そのなかで「ATP合成酵素」がどのようにしてATPをつくるのかについて調べ、久堀先生が助教授でおられた1997年には、当時、研究室の教授・吉田賢右先生のグループが、この酵素が「回転しながら働く」様子を観察するに至りました。
私たちの体内ではミトコンドリアでATPがつくり続けられています。一方で、太陽光を使って光合成を行う植物がもつ葉緑体型のATP合成酵素は、昼間にしか働きません。1日の仕事をいつ始めていつ終えるのか、いったいどういう仕組みで毎日決まった時間に稼働しているのかというと、なんとこの回転しながら働く軸分子には、オン/オフのスイッチがついているそうなのです。
久堀研究室は、ほうれん草の葉緑体を使って、このスイッチの動きを観察する実験を行い、「日の出とともに光合成の酵素スイッチはオンになり、日の入りと同時にオフになる」という結果を導き出します。さらに、植物がもつさまざまな役割をもったスイッチに作用する「チオレドキシン」に関する研究を進め、チオレドキシンがオンにするタンパク質を次々に発見。海外のチオレドキシン研究の第一人者からの称賛を受け、2020年現在も、チオレドキシン研究は久堀先生の研究室が日本でもっとも進んでいるそうです。
それにしても、植物がATPをつくり出すにあたって、太陽光が得られる時間帯はその機能をオンにし、そうでない時間帯はオフにするという「スイッチ」をもっているとは、使わない部屋の電気をちゃんと消しているようなイメージで本当に驚きです。
私たちの体内ではミトコンドリアでATPがつくり続けられています。一方で、太陽光を使って光合成を行う植物がもつ葉緑体型のATP合成酵素は、昼間にしか働きません。1日の仕事をいつ始めていつ終えるのか、いったいどういう仕組みで毎日決まった時間に稼働しているのかというと、なんとこの回転しながら働く軸分子には、オン/オフのスイッチがついているそうなのです。
久堀研究室は、ほうれん草の葉緑体を使って、このスイッチの動きを観察する実験を行い、「日の出とともに光合成の酵素スイッチはオンになり、日の入りと同時にオフになる」という結果を導き出します。さらに、植物がもつさまざまな役割をもったスイッチに作用する「チオレドキシン」に関する研究を進め、チオレドキシンがオンにするタンパク質を次々に発見。海外のチオレドキシン研究の第一人者からの称賛を受け、2020年現在も、チオレドキシン研究は久堀先生の研究室が日本でもっとも進んでいるそうです。
それにしても、植物がATPをつくり出すにあたって、太陽光が得られる時間帯はその機能をオンにし、そうでない時間帯はオフにするという「スイッチ」をもっているとは、使わない部屋の電気をちゃんと消しているようなイメージで本当に驚きです。

植物って人間から見ると止まってるけど、
伊藤亜紗
中ではものすごく動いてる
ときに過剰な太陽からの贈与
地表に降り注ぐ太陽光エネルギーは、全世界で6×10^20(10の20乗)kcalだそうです。こう言われてもパッとイメージできませんが、このうち、植物が光合成で使える可視光と言われるエネルギーは45%。つまり、太陽が地球上の生物に与えているエネルギーのうち、植物が使えるのは半分以下、ということですね。
センターでは、太陽からの贈与の問題について、「太陽は利他だ!」といったように、プロジェクト開始当初からよく話題に上っていて、利他プロジェクトにおいて「太陽」はとても重要な鍵を握っているように思われます。今回も、久堀先生からまずひと通り研究に関するお話をうかがったあと、最初に発せられた伊藤先生のコメントは「最初はすべて太陽から来ていて、スイッチにも光が関係しているというのは、文系的な言い方ですけれども、すごく感動的」でした。そして中島先生は、この「太陽の力を光合成にすべて生かしきれていない」、あるいは「進化の過程で海から陸に植物が出てきたときには、太陽の力、紫外線が強すぎて非常に大変だった」ということから考えられる「太陽の過剰」という問題に関して、久堀先生のお考えを尋ねます。
これを受けて久堀先生は、「夏のほうれん草と冬のほうれん草」について話してくれました。「夏のほうれん草って、色が浅いですよね。冬のほうれん草は、すごく緑が濃い。なぜそうなるかっていうと、冬のほうが光が弱いから、光合成を同じ効率でやるためには、葉緑体やクロロフィルをたくさん作らなきゃいけないわけです。木も、表面の葉っぱと中のほうの葉っぱでは、葉の濃さが全然違うんですね。要するに、過剰に当たるところは、なるべくそれを逃がすように、吸収しないようにする。」
中島先生は、「あんまり植物の世界を人間に応用しすぎる、ぼくたちの人文系の過剰っていうのは、ちゃんと諌めないといけない」とおっしゃっていましたが、この太陽の贈与の過剰とそれに応答する植物のお話を聞いていると、「これも食べ! あれも食べ! これ持って帰り!」とものすごく親切だけれども、まったくお返しなど期待していないお隣さんと、それに合わせて冷蔵庫の在庫を調節している自分のことが想起されました。
センターでは、太陽からの贈与の問題について、「太陽は利他だ!」といったように、プロジェクト開始当初からよく話題に上っていて、利他プロジェクトにおいて「太陽」はとても重要な鍵を握っているように思われます。今回も、久堀先生からまずひと通り研究に関するお話をうかがったあと、最初に発せられた伊藤先生のコメントは「最初はすべて太陽から来ていて、スイッチにも光が関係しているというのは、文系的な言い方ですけれども、すごく感動的」でした。そして中島先生は、この「太陽の力を光合成にすべて生かしきれていない」、あるいは「進化の過程で海から陸に植物が出てきたときには、太陽の力、紫外線が強すぎて非常に大変だった」ということから考えられる「太陽の過剰」という問題に関して、久堀先生のお考えを尋ねます。
これを受けて久堀先生は、「夏のほうれん草と冬のほうれん草」について話してくれました。「夏のほうれん草って、色が浅いですよね。冬のほうれん草は、すごく緑が濃い。なぜそうなるかっていうと、冬のほうが光が弱いから、光合成を同じ効率でやるためには、葉緑体やクロロフィルをたくさん作らなきゃいけないわけです。木も、表面の葉っぱと中のほうの葉っぱでは、葉の濃さが全然違うんですね。要するに、過剰に当たるところは、なるべくそれを逃がすように、吸収しないようにする。」
中島先生は、「あんまり植物の世界を人間に応用しすぎる、ぼくたちの人文系の過剰っていうのは、ちゃんと諌めないといけない」とおっしゃっていましたが、この太陽の贈与の過剰とそれに応答する植物のお話を聞いていると、「これも食べ! あれも食べ! これ持って帰り!」とものすごく親切だけれども、まったくお返しなど期待していないお隣さんと、それに合わせて冷蔵庫の在庫を調節している自分のことが想起されました。
適者生存? それともたまたま?
そして中島先生は、ここで「オートマティカルなもの」と「利他」の話を久堀先生に手渡します。オートマティカル、すなわち「意志の外部によって何かが起動しているもの」。これもセンターの利他プロジェクトではお馴染みになりつつある視点です。近いところですと、3〜4月に行われていたMDLでの中島先生の連続講義の第3回「与格と利他」に、この「オートマティカルなもの」に関するお話が出てきました(コチラからアーカイブに飛べます)。この「オートマティカルな」植物の「オン/オフ」を、我々人間はどう捉えたらいいのか、という中島先生の問いに対して、久堀先生は、「スイッチ」と「土台」の話をします。
緑色植物にはスイッチとそれを支える土台がついているのだそうなのですが、葉緑体の起源であるシアノバクテリアには土台のみしかなく、さらに細菌になると何もついていない。さらに、そのオン/オフの制御をするシステインの場所もいろいろで、それぞれそこでオン/オフを行っているという様相なのだそうです。進化を研究している人たちはこの多様な状態の理由として「そのほうが生きていく上で好都合だったから、そういうものが生き残った」という説明をするそうですが、久堀先生はこれに笑顔で首をかしげておられました。
緑色植物にはスイッチとそれを支える土台がついているのだそうなのですが、葉緑体の起源であるシアノバクテリアには土台のみしかなく、さらに細菌になると何もついていない。さらに、そのオン/オフの制御をするシステインの場所もいろいろで、それぞれそこでオン/オフを行っているという様相なのだそうです。進化を研究している人たちはこの多様な状態の理由として「そのほうが生きていく上で好都合だったから、そういうものが生き残った」という説明をするそうですが、久堀先生はこれに笑顔で首をかしげておられました。
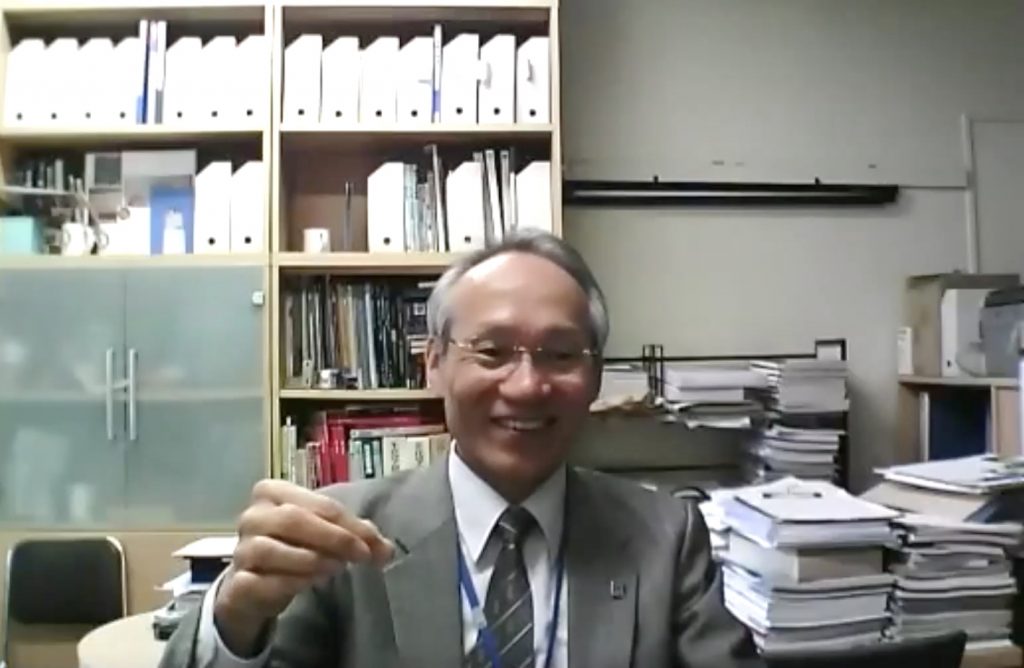
どうしてそんなうまいこと進化したのかな、
久堀徹
っていうのはわからない
ここで伊藤先生が久堀先生に、進化をどう捉えるかという質問を投げかけます。「有利な特性をもった個体が生き残ってきた、っていう考え方と、地球環境なんて偶然の連続なわけだから、そんなに合理的にできてないよっていう、2つの考え方がある気がするんですけども」。久堀先生は、「少なくとも、チオレドキシンで制御されているタンパク質を眺めていると、つねに適者生存で選択圧がかかっているということでは説明できないことが起こっている」と話した上で、次のように答えました。
たまたま、運のいいやつが
久堀徹
生き残ったっていうのが
正解じゃないかな
利他と偶然、曼珠沙華、水芭蕉、座禅草の余裕
ちなみに、このスイッチのオン/オフを担当しているチオレドキシンは、私たちの体内では細胞質に1種類、ミトコンドリアに1種類、合計2種類しかないそうです。一方で、植物には20種類ものチオレドキシンがある。これについて久堀先生は、これが正しいかどうかわからないけれども、と前置きした上で、「植物は環境が変わったからといって、いろんな都合のいいところに逃げていけないから、いろんな武器をもっていて、その時その時で適応できるようになっている」というお話をしてくれました。「今流行りのゲノムもそう。動物に比べれば、植物は圧倒的に多い。見た目には、その辺に生えている雑草の構造のほうが人よりもはるかに単純な感じがするじゃないですか。だけど実はそうではない」。
環境に適応しようとしてそうなった、あるいは、環境に適応しようとして変われたたものだけが生き残った…という説もある一方で、やはり久堀先生にとっては、今のところこういった動物や植物の状態をもっともよく説明する言葉は「偶然」のようです。久堀先生がこの考えについて今西錦司さんの名前を出したのをきっかけに、中島先生はその著書『自然学の提唱』(講談社、1984)に収録されている「曼珠沙華」という短いエッセイの話をします。「地下茎である曼珠沙華(彼岸花)には花を咲かせる理由がない、これは花を咲かせることによって自然体系全体への奉仕をやっている、それは曼珠沙華がもっている“余裕”からくるんだ、という話が出てくるんです。」
久堀先生は「そういうものって、自然界にいっぱいありますよね」と話します。たとえば、水芭蕉や座禅草。これらは、花の真ん中の肉穂花序と呼ばれる部分が、外が10℃以下になっても20〜25℃と温かく、匂いを余計に発するそうです。これは種の保存に有利とも言えますが、久堀先生によると「そこまでしなくたって、水芭蕉いっぱい生えてるし」。「生物学者はそこに合理的な理由をつけたがるんですよ。よくよく考えたら、これ、そんなことしなくたっていいよね、っていう話はいっぱいありますね」。
環境に適応しようとしてそうなった、あるいは、環境に適応しようとして変われたたものだけが生き残った…という説もある一方で、やはり久堀先生にとっては、今のところこういった動物や植物の状態をもっともよく説明する言葉は「偶然」のようです。久堀先生がこの考えについて今西錦司さんの名前を出したのをきっかけに、中島先生はその著書『自然学の提唱』(講談社、1984)に収録されている「曼珠沙華」という短いエッセイの話をします。「地下茎である曼珠沙華(彼岸花)には花を咲かせる理由がない、これは花を咲かせることによって自然体系全体への奉仕をやっている、それは曼珠沙華がもっている“余裕”からくるんだ、という話が出てくるんです。」
久堀先生は「そういうものって、自然界にいっぱいありますよね」と話します。たとえば、水芭蕉や座禅草。これらは、花の真ん中の肉穂花序と呼ばれる部分が、外が10℃以下になっても20〜25℃と温かく、匂いを余計に発するそうです。これは種の保存に有利とも言えますが、久堀先生によると「そこまでしなくたって、水芭蕉いっぱい生えてるし」。「生物学者はそこに合理的な理由をつけたがるんですよ。よくよく考えたら、これ、そんなことしなくたっていいよね、っていう話はいっぱいありますね」。

私たちは偶然なるものである、
中島岳志
というのが利他には重要
ほうれん草という相棒
「いちばんお好きな植物は何ですか」という伊藤先生の質問に、久堀先生は間髪入れずに「ほうれん草です」と答えました。質問にも驚きましたが、あまりにも迷いのない答えにも驚愕しました。しかしこれには大納得の理由があったのです。
光合成の研究で使われる植物は、2000年以降、今に至るまでシロイヌナズナ(白犬薺)が主流だそうですが、それまではほとんどすべてほうれん草で行われていたそうです。70年ほど前にダニエル・アーノン(植物生理学者1910-1994)という人がいろんな植物で光合成の研究を行った結果、ほうれん草は「細胞を壊しても液胞が壊れない」ということに気づき、以来、光合成の研究はずっとほうれん草。どんな家庭でも食卓に上る頻度は少なくないと思われる、あのほうれん草です。こうやって聞くと、自分と同じく地味だと思っていた友達が、実は世界的に有名だったと聞かされたかのような衝撃を受けます。
一度、久堀先生の研究室で、「卒研生が間違えて小松菜を買ってきて全然実験がうまくいかずに悩んでいた」というお話から、ご自身が学生時代だった頃には、市場から50〜100把ほど箱買いして、葉っぱを全部むしってミキサーでつぶす作業が日課のようだったというお話、さらに葉っぱをむしって大量に残った茎をバターで炒めて「ほうれん草に愛をもって」食べておられたお話までをうかがうと、久堀先生のほうれん草愛、並びに光合成の研究者の方々にとってのほうれん草という存在の大きさがしみじみと伝わってきました。
最後に久堀先生は、「試算上は2050年頃に食糧供給が追いつかなくなる」との予想から、もっと生産性の高い植物はどんなものか、もっとよりよく光合成を行うには、どういったところがチューンアップされればいいか、というのを見つけたいというお話をしてくださいました。そして研究者や研究内容によって、その目的はさまざまであるけれども、基礎科学をやっている久堀先生は、「自分がもった疑問に対して、それがストンと落ちればそれでいい」と話します。
久堀先生を囲んだこの度の研究会では、利他とは何かを考えるためのヒントがあちこちにたくさん散らばっていました。それは酵素の働きであり、ほうれん草の生き様であり、そして久堀先生の姿でもありました。最後に、久堀先生のこちらのひと言をご紹介して、第2回研究会レポートは終わりです。
光合成の研究で使われる植物は、2000年以降、今に至るまでシロイヌナズナ(白犬薺)が主流だそうですが、それまではほとんどすべてほうれん草で行われていたそうです。70年ほど前にダニエル・アーノン(植物生理学者1910-1994)という人がいろんな植物で光合成の研究を行った結果、ほうれん草は「細胞を壊しても液胞が壊れない」ということに気づき、以来、光合成の研究はずっとほうれん草。どんな家庭でも食卓に上る頻度は少なくないと思われる、あのほうれん草です。こうやって聞くと、自分と同じく地味だと思っていた友達が、実は世界的に有名だったと聞かされたかのような衝撃を受けます。
一度、久堀先生の研究室で、「卒研生が間違えて小松菜を買ってきて全然実験がうまくいかずに悩んでいた」というお話から、ご自身が学生時代だった頃には、市場から50〜100把ほど箱買いして、葉っぱを全部むしってミキサーでつぶす作業が日課のようだったというお話、さらに葉っぱをむしって大量に残った茎をバターで炒めて「ほうれん草に愛をもって」食べておられたお話までをうかがうと、久堀先生のほうれん草愛、並びに光合成の研究者の方々にとってのほうれん草という存在の大きさがしみじみと伝わってきました。
最後に久堀先生は、「試算上は2050年頃に食糧供給が追いつかなくなる」との予想から、もっと生産性の高い植物はどんなものか、もっとよりよく光合成を行うには、どういったところがチューンアップされればいいか、というのを見つけたいというお話をしてくださいました。そして研究者や研究内容によって、その目的はさまざまであるけれども、基礎科学をやっている久堀先生は、「自分がもった疑問に対して、それがストンと落ちればそれでいい」と話します。
久堀先生を囲んだこの度の研究会では、利他とは何かを考えるためのヒントがあちこちにたくさん散らばっていました。それは酵素の働きであり、ほうれん草の生き様であり、そして久堀先生の姿でもありました。最後に、久堀先生のこちらのひと言をご紹介して、第2回研究会レポートは終わりです。
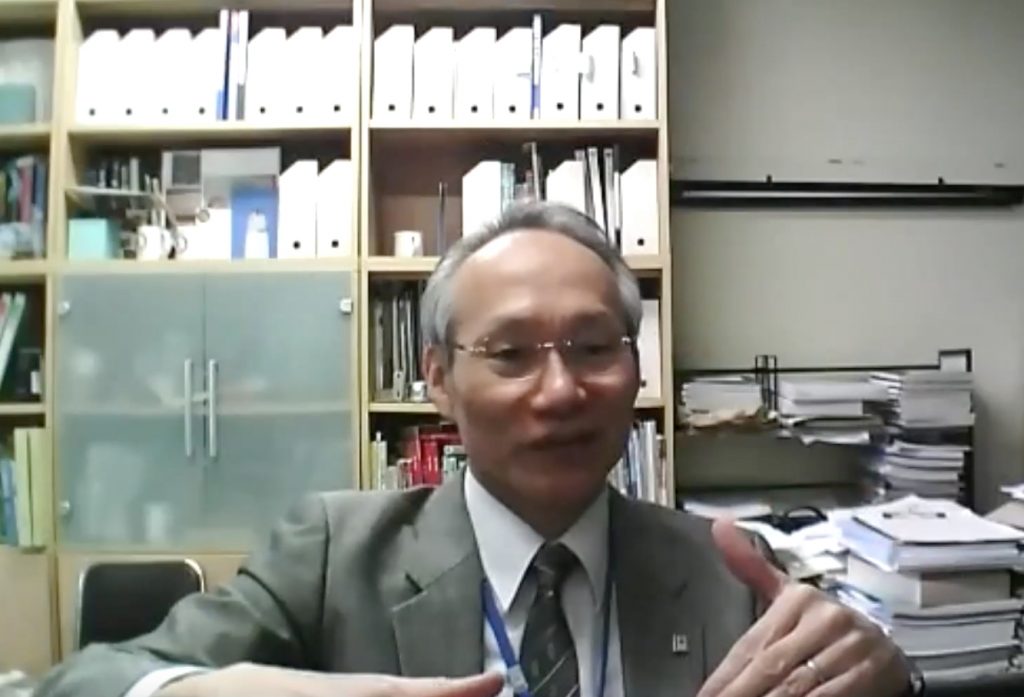
どこまでわかれば自分で
久堀徹
「わかった」のかっていう答えを、
つねに探している
(目撃と文・中原由貴)

