木内久美子さま、山崎太郎さま
「3」の利他的可能性
リレーエッセイの3番手を務めるにあたってまず感じたことは、山崎さん、木内さんから投げられたボールのどちらに反応し、どちらに投げ返そうかという「迷い」でした。二者間の往復書簡であればこのようなことは起こりません。宛先は一つだからです。木内さんが「どちらのお名前を先に書くかしばらく考えました」と最初に書かれているように、そこからまず躓いてしまう。こうした選択は、多くの人にとっても日常的なものなのではないでしょうか。手紙、電話、ポケベル、携帯、Eメール、SNSと通信手段が進化して「1対1」から「1対n」モデルのコミュニケーションが急増した現代社会において、僕たちは日々、宛先の選択を何気なく決定しています(主たる返信先、年長者、役職などなど)。何かここには利他や自他の思考に通ずる要素が潜んでいるようにも思いますが、それは今は措いておくことにしましょう。
*
木内さんから「3」の自他、というパワーワードが飛び出したので、まずそこから反応しておきます。実のところ僕も「3」には何か特別な力があるように思っていました。突然、個人的な話になりますが、うちには子供が3人います。子供たちを観察していると「2」と「3」では、まるっきり違っていて、しばしばいわれる「3人になると社会ができる」という言葉を実感することが多くあります。「1対1」のケンカは強いほうが勝つけれども、3人になると「2対1」になって「強さ」ではない基準でケンカが収束する、ということが頻繁にあります。物であれ優しさであれ、何かを貰ったらその相手に返すという二者間での「贈与交換」ではなく、それがもう一方の第三者へとめぐっていくこともある。
木内さんのエッセイは「3」が導くポリフォニーから、ベケットの『プレイ』のカコフォニー(cacophony)へと話を展開させていきます。ベケットはこの作品の演出で、観客に意味がわからなくてもいい、音=リズムこそが大事なのだ、として俳優に高速でセリフをいわせることで不協和音を混在させたと記しています。このカコフォニーのくだりで僕は1950年代の日本映画のことを想起しました。1960年頃に吉田喜重や大島渚、篠田正浩らの「松竹ヌーヴェル・ヴァーグ」が日本で起こる前に、すでに「新しい波」の兆候は見られていました。市川崑、川島雄三、中平康、増村保造といった新世代の作家たちの登場です。細かい映画史の話は省きますが、とりわけ中平や増村がやったことは、セリフの意味がきちんと伝わらなくてもいいから、発話の速度を限りなく速めるということでした。
面白いことに当時、増村映画『巨人と玩具』(1958年)に出演していた俳優の高松英郎が、これ以上できないというくらいにセリフのスピードを上げるよう監督に演出されました。彼はなんでこんな変な演出をするのだろう、と違和感を覚えつつも仕方なく頑張って演じます。けれども後からラッシュを見てみると、そのスピードに違和感はなく、むしろ日常のリアリティを感じ取ったというのです。つまり、彼は自己を外在化させ、その映像を介して日常のリアリティを事後的に発見したわけです。それまでの日本映画ではゆっくり丁寧に発話するのが当たり前だったけれども、それへのアンチテーゼとして創り出した異質な映像が、逆説的にリアルだと感じさせたという興味深いエピソードです。
しばしば「利他」を考える時、利他/利己、自/他という関係で捉えてしまいがちですが、何かを媒介にした「自己の他者化」(他者の自己化)、あるいは「自己の再帰性」ということも考慮に入れる必要があるのかもしれません。その時、「映像」はいかなる意味を持つのか、どのように作用するのか、自他をめぐる思考は果てしなく拡がっていきます。ともあれ、これもまた今後きちんと考えるべき課題とさせてください。
テクストに巻き込まれる「批評」
自他の境界の流動性に触れた山崎さんのエッセイでは「模倣」や「憑依」といったキーワードが出てきました。考えてみれば、われわれ3人が研究対象としているオペラ、演劇、映画には「パフォーマンス」、すなわち「演じる」ことへの通底する思考があるように思います。役に成る、他者を演じる、日頃からそのような生成変化を常とする芸術を対象としていることもあってか、自/他の境界の流動性に関して響きあうものがあるのかもしれません。山崎さんは「外国語」の学習において「他者をまねる」という指向と、「翻訳」の営みの根底にある「他者を模倣する」という欲望を結びつけ、その上で現在ワーグナーの書簡を訳しながら彼の人間臭く生々しい文体が「乗り移った」ような感覚に囚われることがあると記しておられます。攻撃的なワーグナーが乗り移り、キーボードを叩きながら訳文を唱えて別人格になってゆく山崎さんを想像すると、想像するだけで『シャイニング』のようで完全にホラーなのですが、ともあれ僕も似たような経験をしたことに思い至りました。そのことについて今日は書かせてください。とりわけ、僕にとってそうした憑依なる体験は、もっぱら「批評」において顕著に見られるのです。
*
僕は現在、『文學界』に「椎名林檎論——乱調の音楽」という音楽批評を毎月連載しています。椎名林檎はシンメトリーにとり憑かれたアーティストといっても過言ではなく、アルバムのタイトルの頭文字や収録時間を揃えたり——『勝訴ストリップ』(SS:55分55秒)、『加爾基 精液 栗ノ花』(KSK:44分44秒)——、創作する楽曲のテンポを166.61や111.11に設定したり、あるいはアルバムのタイトル曲の文字数を、真ん中の曲を中心に左右対称に揃えることで有名です(後者のアルバムでは演奏する楽器やメンバーもシンメトリーにするという徹底ぶり)。常軌を逸していると思われるかもしれません。彼女はデビュー当時、好きなアーティストにピーター・グリーナウェイの名前を挙げていました。このイギリスの映画作家は、シンメトリカルな空間を志向したり、フレームを二重化させたりと、フォルム(形式)への異様な執着を見せる衒学趣味の作家で、厳密な規則性と緊張感に満ちた映像を特徴としています。つまり、椎名林檎の音楽と相通ずるところがある。彼女の創作活動においては、この左右対称の美が不可欠なわけです。
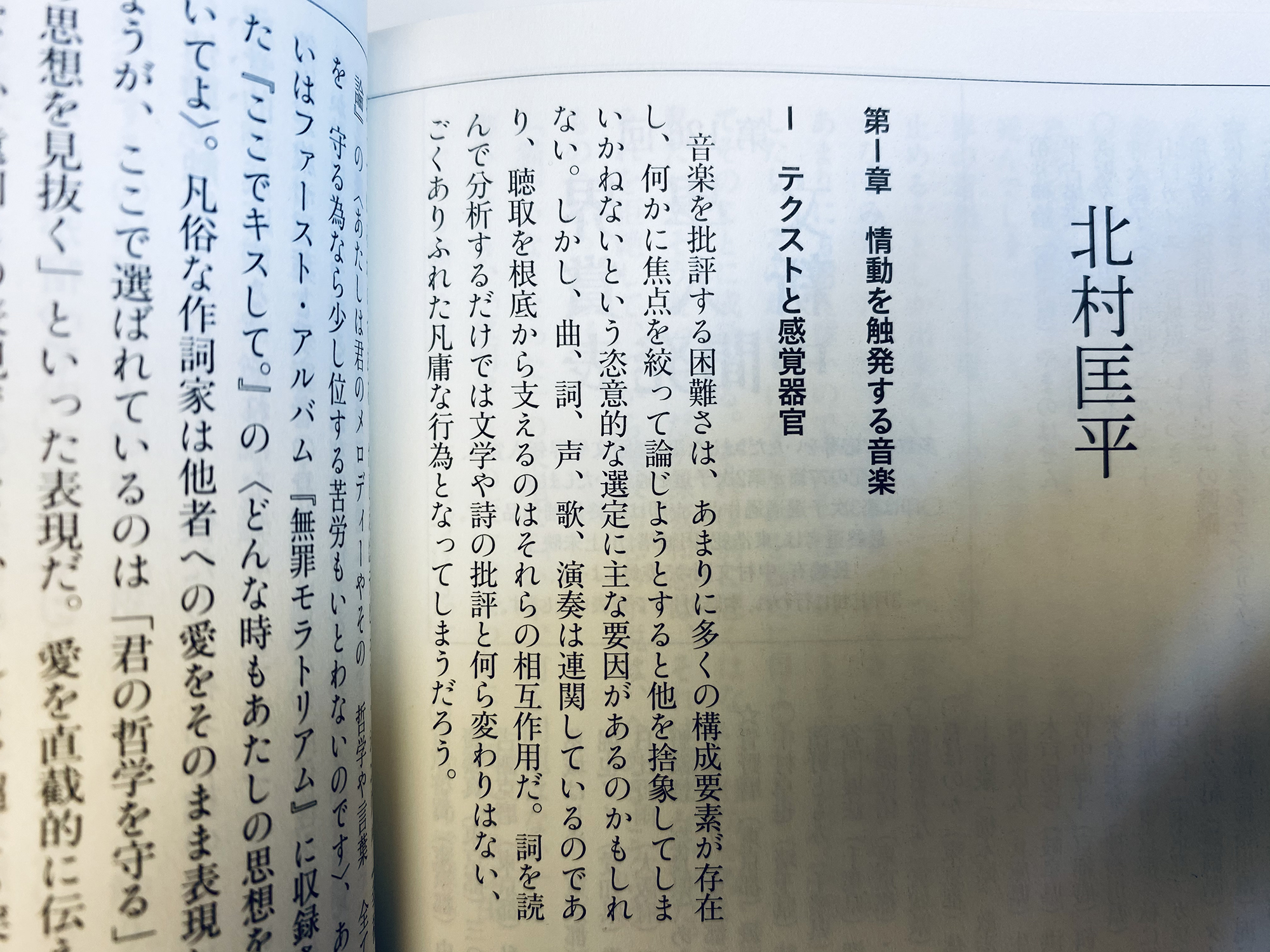 図 1 北村匡平「椎名林檎論——乱調の音楽」『文學界』2021年4月号
図 1 北村匡平「椎名林檎論——乱調の音楽」『文學界』2021年4月号 とはいえ、文字数や頭文字を揃えるということは芸術家にとってかなり創造の自由が奪われることを意味します。でも、それがやめられない。それが彼女にとって「正しい」選択なのです。こうした彼女の創作のプロセスや根底に流れる思想を掘り起こしていくと、驚くべきことにいつの間にか次第に批評するこちら側までも、そのエッセンスに侵食されているのです。椎名林檎は制約を課し、その枠組みの中で創作する。この徹底した身振りにこちら側の「批評」という営みも変質してしまう。いわば文体が文体によって侵されていくような感覚に近いかもしれません。その痕跡をいくつか紹介すると、たとえば図1のように頭文字が意味を為すように並べること(これは違う回の文字列と組み合わされることで別の主題と共鳴するのですが、ここでは触れません)。他にも節の見出しが分析対象のアルバムようにシンメトリカルな文字数になっていたり、〈分裂〉という主題で読み解きつつ文章も分裂を体現していたり……。僕にとって、これはまったく言葉遊びなどではなく、それが対象に近づくための自分なりの批評実践なのだろうと思っています。
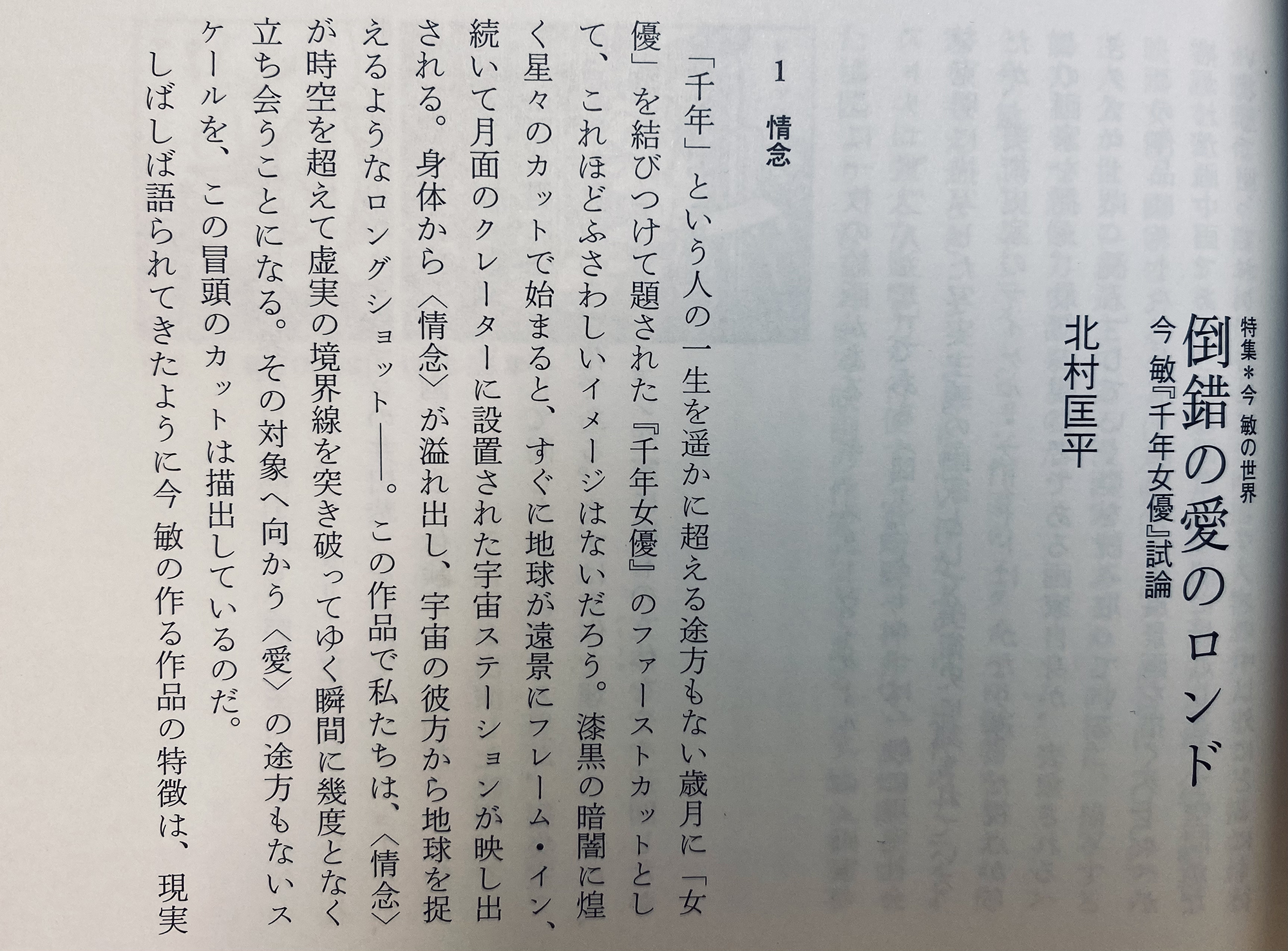 図 2 北村匡平「倒錯の愛のロンド——今 敏『千年女優』試論」『ユリイカ』2020年8月号
図 2 北村匡平「倒錯の愛のロンド——今 敏『千年女優』試論」『ユリイカ』2020年8月号 最近、自分が書いた批評で他にも例を挙げておきましょう。『ユリイカ』の今敏特集号に『千年女優』論を寄稿しましたが、僕の批評はこのアニメーション映画の冒頭のシーンの記述から始まります(図2)。この作品は「循環」や「円環」の図像的イメージが多用され、歴史を超えて人間関係が反復していく作品、「輪廻」や「繰り返し」が重要なモチーフとして描かれています。だから僕の文章の中にもヒロインの重要なフレーズが、何度も反復していくように挿入されます。あるいはこの作品が、登場人物が観ている映画のワンシーンで始まり(いわゆる劇中劇)、最後にはその映画の続きに回帰するように、批評文も映画内映画の冒頭の分析から始まり最後に再び冒頭の映画の記述に回帰します。要するに、これもまた作品の形式が批評を書く「手」に憑依したような創作になっていました。こうした批評実践は、自分では気づかずにそうなっていることが多く、ほとんどが事後的に気づくのです。
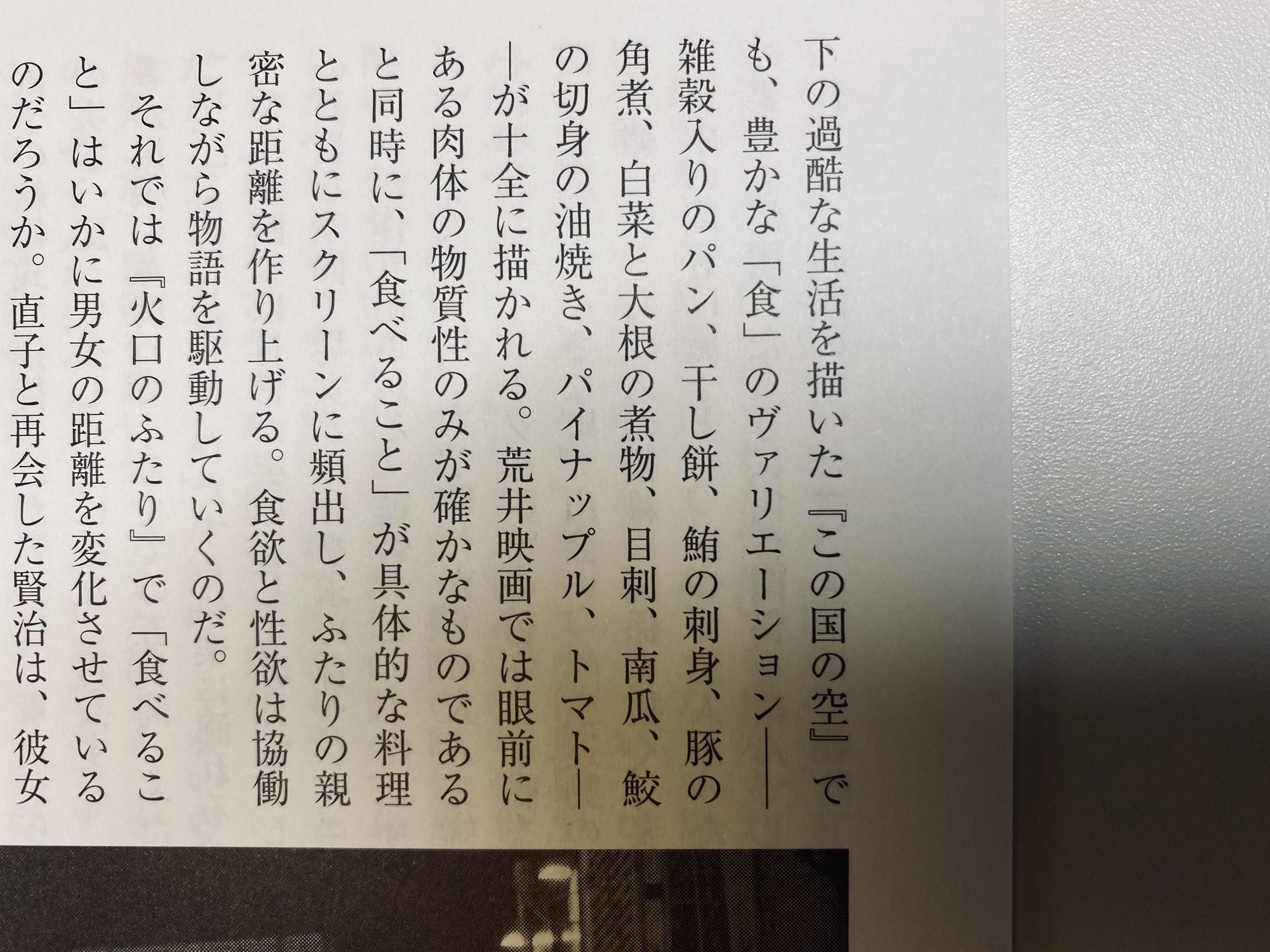 図 3 北村匡平「荒井晴彦が描く〈血〉と快楽——『火口のふたり』試論」『映画芸術』(469号)2019年
図 3 北村匡平「荒井晴彦が描く〈血〉と快楽——『火口のふたり』試論」『映画芸術』(469号)2019年 実のところ、こうした分析対象の文体やエッセンスに、いつの間にか「書く」という行為が「乗っ取られる」ことに対して、長らく無自覚でした。そのことに気づいたのは、ある批評家に指摘されたからです。以前、『映画芸術』に荒井晴彦の『火口のふたり』論を寄稿しました。この映画は、画面上に差し出されるさまざまな料理を主人公たちが「食べること」と、二人の性の欲望、国家の終焉が見事に重なり合っていく作品なのですが、スクリーンに次々に「食べ物」が現れるように、批評の文体においても、映画のシーンのように具体的な食事の固有名詞を詳細に記していく手法を取っています(図3)。意図的に食事の固有名詞を羅列していく方法が、映像に通底する思想を浮かび上がらせていると評してもらって、まったく無自覚だった僕は、はたと膝を打ちました。それは自分ではスタイルを模倣する、という行為とはいささか違う気がしています——いうならば作家固有の創作実践が「批評」(という創作行為)に乗り移ること、むしろ意図せず〈身体=形態〉がハッキングされるような感覚なのではないか。
「論文」と「批評」の違い
批評とは一見すると、書き手が主体的に分析対象を論じていく行為だと思われているかもしれません。けれども、僕にとってはまったく違うものでした。むしろ受動的とすらいえるかもしれません。思い返せば、多かれ少なかれ対象それ自体や、その作品を産み落とした作家の創造的営みに、その都度、自分のスタイルが乗っ取られ、変容しているのです。僕にとっての「批評」とは、およそ「書く主体」と「書かれる客体」という二項対立的なものではなく、「書く」という営みが、作品/作家のエクリチュールに絡め取られ、巻き込まれてゆくようなあり方です。このようなことは不思議と「論文」ではいっさい起きません。
ここで「論文」と「批評」の違いに紙幅を割くわけにはいきませんが、前者は基本的にきわめて客観的でなければならず、分析対象から書き手は切り離されていなければなりません。人文学といえども限りなく主観性を排除し、第三者が見ても同じように検証でき、客観的な結論に導かれなければならないからです。「論文」とは極端にいえば、分析対象と明確な距離を取り、変容を拒み、侵犯を許さない厳密にして頑なな振る舞いにほかなりません。
一方、僕にとっての「批評」とは、対象との距離を見失い、主/客の関係が突き崩され、テクスト同士が饗応関係にあるもの、いわば創造的営みが乗り移って自/他の境界が融解するような実践です。あるいは能動/受動を切り分けることができない、分かち難く結びついている中動態的なものなのだということもできるでしょう。しばしば学者や研究者という存在は、超越的な立場から物事を捉え、語ろうとします。学問の世界において自/他の境界はいかにして動いてゆくのか、そんなことをお二人とのやり取りを介して、考えてみたいと思っています。

